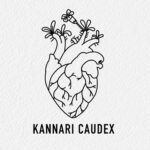こんにちは、金成コーデックスです。
数あるアガベの中でも、小型で葉先の棘が長く伸びるタイプの人気種「Agave utahensis v. eborispina/アガベ・ユタエンシス・エボリスピナ」の種子を入手したので、実生栽培の記録を残したいと思います。
Contents
Agave utahensis var. eborispina/アガベ・ユタエンシス・エボリスピナの特徴
私はこれまでに近縁種の「Agave utahensis var. nevadensis/アガベ・ユタエンシス・ネバデンシス」「Agave utahensis var. utahensis」の実生栽培を行っており、耐寒性の高さから私の住む東北でも育てやすいアガベとして気に入っています。
この投稿をInstagramで見る
因みにエボリスピナとネバデンシスの違いは「産地」と「棘の色や長さ」
エボリスピナは棘が白く長いものが多く葉は黄緑色、ネバデンシスはエボリスピナに比べて棘が黒く、葉も青に近い緑色をしています。エボリスピナの中でも棘がうねっているのを「陽炎」と呼んで高額で取引されているのを目にしますが、棘が派手な動きをするのがエボリスピナの特徴です。
アガベ・エボリスピナの実生栽培記録
エボリスピナの種子の入手

私は過去に何度かアガベ・エボリスピナの種子をメルカリで購入したことがありますが、いずれも偽物でした。
(いい加減学びなさいよ、、と自分でも思います汗)
この経験から、基本的に国内外のどこかでエボリスピナの種子の販売がない限り、個人でアガベ・エボリスピナの種子を入手してメルカリで売ることは(ほぼ)あり得ないと思っています。海外であろうが国内であろうが販売の形跡があって、その種子を転売している場合は本物の可能性がありますが、どこでも取り扱ってないのに個人でエボリスピナの種子を販売する人がいたら疑ったほうが良いと思います。特にヤフオクとメルカリ。
以前はseedstockさんでも販売されているのを見たことがありますが、2020年6月現在では品切れ中です。(※追記:2022年6月にseedstockさんで再販されました。私の現在のエボリスピナの実生はこの種子由来です)
播種~発芽
この投稿をInstagramで見る
詳しい播種の経過は上のインスタグラムの中でも書いていますので、そちらをご覧いただけると分かりやすいと思いますが、播種から発芽まで4日かかりました。

※種子をオーソサイドで殺菌しているところ
播種から発芽までの流れは以下の通り
- 播種前に種子を殺菌剤(オーソサイド)に半日浸水(※ダコニールでもOK)
- 播種用の用土は赤玉&日向土。表土にバーミキュライト1cm程度
- ヤカンでお湯を沸かして用土と鉢(プレステラ90)を熱湯消毒
- 用土が冷めたらバーミキュライトの上に種子を並べる(※覆土はしない)
- プラケース(ダイソーの200円のシューズボックス)で腰水管理(水多め)
- 高湿度をキープするために隙間を少し開けて蓋をする
- 温度はMAX28℃、MIN18℃
という条件でした。
実生栽培7日目:あらかた発芽したら蓋を外す

これは個人的な感覚ではありますが、実生栽培で発芽を促すために腰水&蓋で湿度を高めていますが、発芽した後もその環境を継続すると子葉が徒長しやすいように感じています。
そのため、だいたい生えそろったら蓋は外して極端な加湿にならないようにすることが多いです。
上の画像は以前のもので表土をバーミキュライトにしていますが、現在ではほぼ育苗用の赤玉土細粒(芝の目土)を使うことが多くなりました。
今回のエボリスピナに関しては、ガラス温室内でLEDをしっかりあてて育てたので、腰水をしたまま実生4か月目まで寄せ植え状態にしていました。
その時の光や風の状況によってはずっと腰水状態でも徒長せずに済むこともあるので、この時期の育て方はケースバイケースかと思います。
セルトレーに鉢上げ
実生4か月が経過して、ある程度大きくなった苗をセルトレーとプレステラに鉢上げしました。
もう既にトップスパインが長く、他のユタ系アガベに比べても明らかに違うのが、もう半年足らずで見て取れます。
エボリスピナの耐寒性は高く、このサイズになれば氷点下前後でも全然平気なので、ビニールハウス内で越冬してもらおうと思います。
まとめ
本記事ではアガベ・ユタエンシス・エボリスピナの実生栽培の経過を報告いたしました。
状況に変化がありましたら、随時更新してまいります。