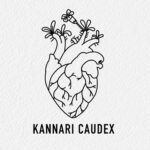こんにちは、金成コーデックスです。
園芸をやっていると色んな害虫や病気に直面することがありますが、中でも駆除が難しいものとして周知されているのが「カイガラムシ」です。
育てている植物にびっしりとカイガラムシが付いているのを見つけると発狂しそうになりますよね。
園芸を長年やっている猛者たちにとっては「またこいつか」というくらいよく見る存在ですが、やっぱり見つけて嬉しいものではないのでそれぞれの方法で皆さん駆除していると思います。
以前、田舎暮らしサイト「おしえて!田舎センセイ」の方でもカイガラムシについてまとめたことがあるのですが、このサイトの方でももう少しわかりやすく簡潔にカイガラムシの正体と駆除方法についてまとめておこうと思います。
初めてカイガラムシを見つけた人に向けての内容になるので、歴戦の猛者たちには当たり前のことばかりかもしれませんが是非お付き合いください。
この記事ではカイガラムシが葉にびっしりついている写真が載っています。見ていてあまり気持ちのいいものではないので、虫が苦手な人はご注意ください
カイガラムシってどんな虫?
まずざっくりとカイガラムシについての情報を書いてみます。
・草とか花より、観葉植物・庭木・果樹につきやすい
・全世界7000種類以上いて、日本には約400種類くらいいるらしい
・ほとんどが動かない雌(♀)で、雄(♂)は翅があって交尾のために飛んで移動
・種にもよるけどメスだけの単為生殖も可能。メスだけでも増える
・暗くて狭い風通しの悪い場所を好む
・成虫には薬剤が効きにくい(※幼虫は薬剤の効果がある)
・メスの成虫の死骸を残しておくと、そこからも孵化するので注意が必要
・ベトベトする排泄物を出し、すす病やこうやく病の原因になる
・排泄物は甘いのでアリが寄ってくる
・カメムシ目の吸汁害虫ではあるが、植物を直接的に枯らすことはほぼ無い
カイガラムシの厄介な点は「どこからともなくやってくる」「気が付いた時にはびっしり付いていて気持ち悪い」「薬剤が効きにくく駆除・防除が難しい」というところ。
おそらく”成虫は動かない”というのも存在に気づきにくい原因で、移動できる幼虫は小さすぎて目視するのは至難の業なんですね。だから気付いた時にはもう沢山ついちゃってるんでしょう。

※葉の裏についたヒラタカタカイガラムシ
単為生殖ができるのでメスだけでも卵を産んで増えるうえに、なんと潰した死骸から子を孵化させられるので、完全にこそぎ落とす or 物理的に除去した後に追いうちで薬剤散布するなどしないと殲滅できない。
そもそも成虫は蝋とか殻を身にまとってるので基本的に薬剤が効きにくい。
といった厄介な特徴を併せ持つのがカイガラムシなんですね。
カイガラムシの種類

日本国内には400種類ほどいると言われてるカイガラムシですが、種類は大きく分けると5~6種類に分類できます。
・白い粉を被ったようなタイプ
・蝋でおおわれているタイプ
・堅い殻がついているタイプ
・殻が無いタイプ
・袋に入っているタイプ
私が育てているパキポディウムについていたのは、ヒラタカタカイガラムシ(Coccus hesperidum)という「殻が無いタイプ」の種類ですが、この種類は「卵のうが無く卵はすぐ孵化する/雄はいない/薬剤の効果が低く逆に天敵となる虫が減少することで多発することもある/温室で発生しやすい」などの特徴があります。
種類によって特徴も違うのですが、種類自体がかなり多く鑑別するのは難しいため、そこまでカイガラムシの種類を気にする必要はないでしょう。基本どのカイガラムシも防除しにくいですし、各々でできる対策には限りがあります。
他にもよく見かけるのが「コナカイガラムシ」
な、、、何も見てないぞ俺は、、 pic.twitter.com/ynRsiiWDXV
— 田舎センセイ (@inakasensei) December 1, 2020
こいつはどこかの園芸店からネット購入したスキンダプサスやマドカズラなどの観葉植物についていました。本当に、、、厄介。見なかったふりをしたいけど、見てしまったらやっぱり駆除しないといけないので凹む。
カイガラムシが原因で起きる病気や症状
カイガラムシが厄介なのは、葉を吸汁してしまう事よりも様々な植物病原ウイルスを媒介するという点。
特に「すす病」と「こうやく病」はカイガラムシによって広まりやすい病気のTOP2です。

上の写真は私の育ててるパキポディウムの葉にヒラタカタカイガラムシがつき、その排泄物がすす病菌とともに広げられているところです。
カイガラムシのベトベトした排泄物はすす病菌に侵されやすく、一度広がると葉が真っ黒になってしまい、美観が損なわれるだけでなく光合成ができずに植物が弱ってしまいます。

※すす病に侵されたパキポディウムラメリーの葉
私のパキポのいくつかはカイガラムシによってすす病を広げられて真っ黒になってしまいました。

カイガラムシの対策・駆除方法

防除の難しいカイガラムシですが、ツイッターで園芸アカウントの皆さんに「カイガラムシを発見した時のファーストアクション」を聞いてみました。
植物アカの皆さまにご質問です。
もし育ててる植物にカイガラムシがついてるのを見かけたら、ファーストアクションは何を使いますか?(※薬剤が効くカイガラムシの幼虫だと仮定します)
皆さんのお勧めの薬剤を教えてください!— 田舎センセイ (@inakasensei) August 12, 2020
選択肢の数に限りがあったので上記のような結果になっていますが、選択肢にないものに関しては数名の方々がコメントで使用薬剤を教えてくださいました。
ただ、一番多いファーストアクションは「テデトール(手で取る)」で、成虫に薬剤がほとんど効かないのを知っている方が多いので、爪楊枝や歯ブラシでこそぎ落とす物理的防除を薬剤を使う前にする人が多いようです。(※私もまずは手で取り除きます)
テデトールをやった後の薬剤としては、以下が回答として出てきました。
・オルトラン
・ベニカスプレー
・マシン油乳剤
・カイガラムシエアゾール
・コルト水和剤
・アクテリック乳剤
・石灰硫黄合剤
・モスピラン
薬剤の適用をみると、私が育てているようなアガベ、ユーフォルビア、ビカクシダ、ハオルチア、パキポディウム、リトープスあたりは、実は上記の中では「カイガラムシエアゾール」しか適用がありません。
自分で選択肢に入れておきながら、パキポディウムなどの園芸・観葉植物にはマシン油乳剤やオルトラン水和剤などの適用はないんですね。
使える薬剤の選択肢が少ないというのもカイガラムシが駆除しにくい点のひとつと言えます。
また薬剤を使用する際には有効成分の違いによる混用の注意などもあり、使用前にしっかりと調べる必要があります。
例えば庭木類に適用のある「アクテリック乳剤」の場合は、ピリミホスメチルというガス効果で速効性が強いのですが、同じくカイガラムシ防除で使うことの多い「石灰硫黄合剤」「ボルドー水和剤」などのアルカリ性の薬剤との混用ができません。
マシン油乳剤はカイガラムシの呼吸口を塞いで窒息死させる効果がありますが、可燃性で保存に注意が必要なのと、雨が降ってしまうと効果が薄れてしまうなどの特徴もあります。
スプラサイドやモスピランは劇物なので素人には使用が難しいです。
以上を踏まえると具体的な対策・防除手順としては以下のようになると思います。
①目につく成虫を全て歯ブラシなどを使ってこそぎ落とす
②カイガラムシが好む環境条件をすべて取り除く(特に風通しに注意)
③適した薬剤(初心者はカイガラムシエアゾールがおすすめ)を散布する
第一には発生させないような環境づくり、それでも発生してしまったら目に見える範囲の成虫のカイガラムシを物理的に駆除、最後に薬剤を散布してより小さい幼虫などもまとめて駆除するというのが正攻法かなと思います。
前述の通り「死骸からも孵化する」ので、カイガラムシを潰し終わった葉を完全にきれいにする必要があるのは言うまでもなく、切り取った葉や枝を近くに放置するのも良くありません。完全に廃棄してしまいましょう!
カイガラムシに関してはこちらの記事もおすすめ!
私が園芸に片足を突っ込み始めた頃から参考にさせていただいている「スーパーサボテンタイム」さんが、私がカイガラムシを発見したタイミングでちょうど記事を書かれていました。
#ブログ更新
【閲覧注意】ビカクシダにつくベトベトとカイガラムシのタイムラプス観察と幼虫の動画 | スーパーサボテンタイム※あのベトベトはどこからくるのかという話。閲覧注意なんですが、検索しても見つからないし、とても貴重な動画が撮れたとは思います。https://t.co/SgUPfFcpri
— スーパーサボテンタイム (@SabotenTime) August 18, 2020
カイガラムシの様子がより鮮明に分かる動画を記事内で投稿くださっているので大変参考になりました。
是非スパサボさんの記事もあわせてご覧くださいね!
まとめ
最近は様々な害虫の駆除情報などをググっても、アルゴリズムの関係で検索結果のほとんどが殺虫剤の企業や公式ページばかりになっています。
園芸をやっていて「この方法が効果ある」という園芸の先輩たちの経験や知識の方が欲しい場合もあるので、今回ご紹介したツイッターアンケートの様なものも参考にしてみるのも良いと思います。(※使用薬剤の適用などの情報は各自で販売元のページに行き確認ください)
カイガラムシは植物を枯らす直接的な原因にすぐになるわけではありませんが、発見した環境は改善する必要がありますし、被害が広がる前に対策をとった方がいいのは間違いないでしょう。